
���m�R�s�O�a���p����
���勴����

���m�R�s�O�a�����J
���o�~�c�_�Еt�߂���
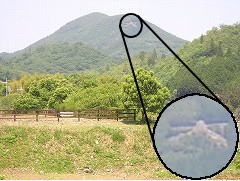
�R�s�K������
 ���m�R�s�O�a���p���� ���勴���� |
 ���m�R�s�O�a�����J ���o�~�c�_�Еt�߂��� |
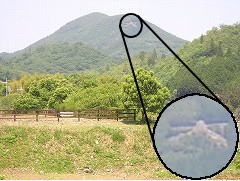 �R�s�K������ |
�@�O�g�̍��̕��Ɍ��Ƌ��s�{�̋��ɂ���R�B�R���ɗ��ƒO�g�̒��S�ƌ�������������B�����̓o�R�R�[�X������B
�T�J������e�R�[�X
|
�͒J�i�R�s�j�R�[�X |
���J����̃R�[�X
|
�@�p������L�����ɉi��15�i1518�j�N�̔N�L�̂���u���q�R�חю��G�}�v������A���q�R��4�`6�V���`����Ă���Ƃ����B
�@�퍑�����`�����ƌ�����c�����i1648�j�N�̉��t�̂���u���X�ؒJ���L�v�ł͓V�c�S�ɂ��������̎R���Ƃ��āu�l�_�y�R�v�Ə����B�R���͎��̏��ݒn�Ɉ��ނ��Ƃ�����B�܂��A���X�ؒJ���L�ł͎l�_�y�R�ߖT�̒n���Ƃ��āu�e���v���o�ꂵ�A����͌��݂̓p�����Ǝv����B�����͉_�ƂȂ��Ă���A�O�g�u�ȍ~�Ŏ��q�R�ɂ������Ƃ����u�������v�Ƃ͈قȂ�B�܂��A�_�̏��ݒn�Ƃ����u�V�c�S�R�����v�Ƃ��������͑��Ɍ����Ȃ��B���X�ؒJ�͓p�����Ɠ����V�c�S���i���m�R�s���j�ł͂��邪���m�R�鉺���k�ő�������Ă���B����6�i1794�j�N�̒O�g�u�ł͎R�Ƃ��āA�܂��R���Ƃ��Ģ���q�R��Ə������B�R���Ƃ��āu�V�J�N���v�ƐU�艼�����t���Ă���B�O�a���j�i1995�j�͍��X�ؒJ���L�̎l�_�y�R�_�ƒO�g�u�̎��q�R�������A�X�ɕ����N�ԌÏ�Ռ���}�G���ɂ���Ƃ����ו����A���q�R�חю��G�}�̎��q�R�חю���̎����֘A�����ł͂Ȃ����Ƃ��Ă���B�]�ˎ��㒆���`����̍�ƌ�����n���ɓ`��鍌���H�G�}�ł́u���q�R�v�Ə������B����24�i1897�j�N�̎O�p�_�_�̋L�́A���́u���q�R�v�ɐݒu���邱�̎O�p�_�Ɂu�l���R�i���ނ��܁j�v�Ɠ_����t���B���{���j�n����n�͎��q�R�����ʏ����Ţ�l���q�R�v�Ə����B���y�n���@��2010�N���݁A�u���q�R�i���������܁j�v�Ƃ��Ă���B���y�n���@�ō̗p���Ă���n���͒n���̖��ꂩ��̏�\�ł���B�O�a���j�ɂ́u���������܁v�ƐU�艼��������B
�@���I���j�i1987�j�́u�l�����R�v�Ə����A�t�����i���E�O�g�s�j�쐣�A���I���i���E�R�s�j�K���A�O�a���i���E���m�R�s�j�̒��o�Ɠp�����̎l�����ɋ���ڂ���䂦�̎R���Ɖ����B���c�i1995�j�͓_�̋L�́u�l���R�v�̎��������A�n���i�����I���j�̌ØV�̈ӌ��Ƃ��ĎR�s�K���̑��A���m�R�s�i���O�a���j���̓c�m�J�A���o�A�p���̎O���������킹�Ďl���������q�R�̖��̗R���Ƃ���B
| ���q�R���͂ލs���P�� | ||||||
| ���� | �ߐ� | �ߑ� | ���� | |||
| ���� | �y�� | �� | �� | �厚 | �s���� | |
| �p�� | �p���� | �p���� | �p�� | �p���� | �p�� | ���m�R �i�O�a�j |
| ���� | �i�����o�j | �i���o�j | �� | ���o | �� | |
| ���� | ���� | |||||
| �c�m�J | ���� | �c�m�J | ||||
| ���R | �K�� | �K�� | ���R | �K�� | ���R | �R �i���I�j |
�@�����̐��͘_���������ł���̂ɒ��g���قȂ邱�Ƃ����������������B�l���i�Ӂj�܂ł����ǂ݂ł���̂ɁA�����P�ǂ݂ƌ����̂��s�R�ł���B���I���j�̐��́A�t�����i���E�O�g�s�j�쐣�i�쐣�J�j�͖k�[�̖쐣���i�ԓy���j�ł����q�R�̎R������Ő����1.7km��ɗ���Ă���A���q�R�̎Ζʂ𗣂�Ċ��ɗŐ��͕��R�ŁA�Ԃɉ͒J��/�c�m�J�������݁A���q�R�����͂ގl�����ɉ�����ɂ͗���߂��Ă���B�����E�ߐ��̍s���P�ʂƂ��Ă̍����o����p��������K�����ɑΉ�����̂́A�쐼�Ζʂł͖쐣�J���ł͂Ȃ��c�m�J���������͍������ł������B
�@���c�i1995�j�̐��ł͓p�����ɑΉ�����������͒��o�Ɠc�m�J���܂��Ă������œ����̎��q�R���Ζʂ̒����i�������j�̖����l�����̒��ɓ����Ă��炸�A���Ɍ����̖��͌K���i�K�����j���܂ޑ��R���ł������B���o�����čs���P�ʂ𑵂����2km�߂������ꂽ�������̖쐣�J�������邩�A���������邩���Ȃ���Ύl�����ɂȂ�Ȃ��B���I���j�i1987�j�ł����c�i1995�j�ł��������Ă��钆�o�́A�����ƕ������Ă������̗̈�͌����ɂ͎��q�R�R���ɐڂ��Ă��Ȃ����A�ō��n�_�̔���R�͎��q�R�R���܂ł̋�������550m�Ŏ��q�R�̉q��ƌ�����ʒu�ł���A�쐣�J�̎��q�R�ɍł��߂Â����ꏊ�ɔ�ׂ�Ύ��q�R�̈�p�ƌ��������ł͂���B���o�n�悪���q�R�k���Ő��̓����i���여��j�ɒ���o�����Ƃ�A��������쑤����z����Ɩk�����܂����s�{�łȂ����Ɍ��ł��邱�ƂɌ�����悤�ɁA�l�דI�ȑ��E�͂��̒n��ł悭�����邪�A�c�m�J�Ɩ쐣�J�Ɋւ��Ă͂��̂悤�ȗ��j�I�o�܂�������nj��Ɍ��Ȃ��B�ߌ���̑厚�̋敪�ł͎��q�R�́A���o�ɒ��������������̂Œ��o�E�c�m�J�E�p�����E�K���i�͒J�͌K���Ɋ܂܂��j�̎l�̑厚�̋��E�ɂȂ��Ă���B�������厚�͊��ɑ��ł͂Ȃ��A���q�R�̖��͂�����O���炠��B���q�R�̎R�������L���Ă���ƌ������Ƃ������ɉ��߂��āA���o�������Ē�����������A�����ߐ��ł��l�����ƌ������ƂɂȂ邪�A�`���Œ��������グ��ꂸ�ɒ��o�����グ���Ă���̂͂ǂ����M�p�ł��Ȃ��B�܂��A�l�����������Ƃ��Ă��A�Ȃ��u���q�v�ƕ\�L����A�u��������v/�u��������v�ƌĂ�Ă��邩����������Ă��Ȃ��B
�@�V��i1987�j�͍��X�ؒJ���L�̒��̎l�_�y�R�̕\�L���A�������̒���Ђɕ�[�����_�y����̎��ł͂Ɛ������Ă���B���q�R�̉��ɂ��Ă̓N���̒f�R�E���E�����̈Ӂi���q�Ȃǁj�ƁA���ӂɓ����̖���p�����n���������i�T�J�E���̕@�E�����Ȃǁj���Ƃ���A�u���̏Z�ތ������R�v�̈ӂƉ����B�܂��A���X�ؒJ���L�ł̎l�_�y�R�_�̏��ݒn�Ƃ����V�c�S�R�����ɂ��āA�����˂��Z�l���J���R�����Ƃ������ƂƓ����悤�ȈӖ������ł͂Ɛ������Ă���B
�@�c�����i1994�j�͌Ñ�̓S�Ɋւ��R���ł͂Ȃ����Ɛ�������B���q�R�́u���i�����j�v�́u�X�J�i�F���j�v�̓]�ŁA�^�^�����S�ɗp���鍻�S���̎�ł���ꏊ�Ƃ������Ƃ̂悤�����A���S�ɊW�Ȃ��Ƃ��F���͂���̂ł͂Ȃ����B�u�F���O���v/�u�F���N���v�ƌÌ^���l����Ƃ��āA���̏F���Ƃ͂ǂ����A�F���ɃO��/�N�����ǂ��ւ���ĎR�̖��ƂȂ��Ă���̂��Ɍ��y���Ă��Ȃ��̂́A�R���𐄑�����ɂ��Ă��ւ��Ȃ��߂��̂悤�Ɏv����B���R�̂܂܂̒n�`�ł�������ڗ��F�̏o���Ă������ȏ��́A�R�n�Ƃ��̊Ԃ̏����ȕ��삵���Ȃ����q�R���ӂɌ�������Ȃ��B���S��Ղ����q�R�����͂ޛ����@��/�͒J��E����̗���ɂ���Ƃ����b�������Ȃ��B���S�_�Ƃ����������V���J������哰���K���ɂ��邱�Ƃ����q�R�̖����S�Ɋւ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����T�Ƃ��Ă��������Ă��邪�A�K���̔����哰�͎��q�R����͒J��Ɣ��������z�����n�`�I�ɗ��ꂽ�ꏊ�ɂ���B�F���Ɠ��l�ɁA���S�Ɩ��W�ɔ�����V���J���邱�Ƃ����R���������낤�B
�@�O�g�u�ɂ͎R�[�̓p�������ɂ��āu�����j���m�q ���m�q ���m�q�g�e �ÎO�c�m�q�A�� �����s����׃��Ճ��� ��Óԑq�m�Î����s�� ���Ãm�R�g�i���w�V�v�Ƃ������B�p�����ɂ͒��̑q�i�C�m�N���j�E���q�i�I�O���j�Ƃ�������������B���q�R�Ɍ����i�F�쌠��/�F��_�Ёj�A���q�ɕs�������A���̑q�Ɉ�א_�����ꂼ��Ղ��Ă���悤�ɓǂ߂�B�������ӏ��ɐ_��������͐l�ނɂ�����x���ʂƎv����̂ŁA���q�R�́u�q�v�ɂ��Ă͒��̑q�E���̑q�ƕ��ԁA�V��i1987�j�̐��@�̒ʂ艽������n�`�̌������ӏ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ����ƍl�����B���ɁA���̑q�A���̑q�A���̑q�ƎO�̑q�̒n�����p�����̒��ɏW�܂��Ă���̂̓N���̌`�����ʂ��Č����Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă݂��B
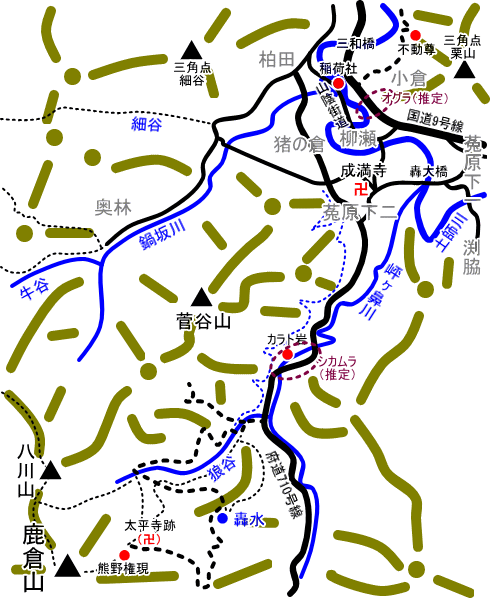 �@���q�R�ɂ͎��̎����������Ă��邪�A�u���̑q�v�ł͓����̎��������Ă���Ƃ������g���Ă���Ƃ��Ƃ�Ȃ��B�R�Ԃ̏W���̍X�ɏ����ł͒O�g�u�̒ʂ�A��Â̓ԑq�ł�����܂��B���������ԑq�i�݂₯�j�Ƃ́u�q�v�̉����Ⴄ�B�p�����̋��q�͓p�����ڂ̏W���̒��S�̐������̂��ɂ��������Ƃ������H�G�}���番����B�u���̍��i����j�v�ƍl���Ă����������Ă���Ƃ��A���������������K���l��鏊�ƌ����̂��������Șb�ł���B�C�m�N�����i���j�̃N���i���j�A�I�m�N������i��j�̃N���A�V�J�O���́A���ށi�k���ᰂ�������E�����߂��ʂ̃V�J�j������܂������̂ł͂Ȃ����ƒn���p��ꌹ���T���N�_�ɂ܂��l���Ă݂��B
�@���q�R�ɂ͎��̎����������Ă��邪�A�u���̑q�v�ł͓����̎��������Ă���Ƃ������g���Ă���Ƃ��Ƃ�Ȃ��B�R�Ԃ̏W���̍X�ɏ����ł͒O�g�u�̒ʂ�A��Â̓ԑq�ł�����܂��B���������ԑq�i�݂₯�j�Ƃ́u�q�v�̉����Ⴄ�B�p�����̋��q�͓p�����ڂ̏W���̒��S�̐������̂��ɂ��������Ƃ������H�G�}���番����B�u���̍��i����j�v�ƍl���Ă����������Ă���Ƃ��A���������������K���l��鏊�ƌ����̂��������Șb�ł���B�C�m�N�����i���j�̃N���i���j�A�I�m�N������i��j�̃N���A�V�J�O���́A���ށi�k���ᰂ�������E�����߂��ʂ̃V�J�j������܂������̂ł͂Ȃ����ƒn���p��ꌹ���T���N�_�ɂ܂��l���Ă݂��B
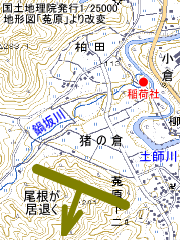 �^�̑q�̒n�} |
 �J���g�� |
 ���q �i���Ɏʂ�R�n�j |
�@���̑q�A���q�ɂ��Ēn���̕��Ɏf���Ă݂��B���̑q�ɂ��ẮA�u���ł��o����v�Ə��Ȃ���p�����ڏW���̖k�����A����ȓ�̕��R�Ȑ��c�n�т��w���Ƌ����Ă����������B���̐��c�n�т͍]�ˎ���ɍ��������䍪���H��������Ă��琅�c�ɂȂ����ƌ����B�y�t��̐��ʂ�肩�Ȃ�̍����̂����n�ŁA���͐����̈������R�n�������悤���B��������̒n�}�ł͒����ɌK�����`����Ă����B���͑S�������Ȃ��B���c�̒��ɑ�₪����ƌ������Ƃ������B�u���̑q���������v�ƌ��������͈�����悤���B�����̏ꍇ�A���q�R�������f���ɉ��т�T�����̎R�n���p�����ڏW�������œˑR�r��Ēi�u���`�����A�y�t�삩�猩��ƎR�n�������Ă���l�Ɍ����āA���̂�����R�Ǝw���u���ނ��i���m�N�j��i���j���i���j�v�ł͖����������ƍl���邪�A�����u��̂��v���A��������ɂ͂������悤�����A�X�ɌÂ����ォ�炠�����̂��ǂ������悭������Ȃ��B���m�R�s�ׂ̗̈����s�s�X�n�̈�q���i���̂��炿�傤�j�����͗R�ǐ삪�ɂ₩�ɖk�ɝ���œ쑤�̎R�n�Ƃ̊Ԃ��J�������n�̒����Ɉʒu���鑺�ł������B
�@���̑q�̂͂���̓���E�݂̓y�t�썇���_�t�߂̋��X���i�R�A�X���j�̘e�̏��u�ɌÂт���Ђ��������B���c�̂���i�u���牺��āA���X���i�R�A�X���j���y�t�쑤�ɂ��邱�̈�ׂ̂���u�́A�����ɂ͒��̑q�ɂ͊܂܂�Ȃ��悤�����i���̑q�n��͎R�A�X����萼�����Ƃ����j�A�p�����ň�ׂƂ����������������悤�ł���B
�@���q�ɂ��Ă͍���9�����̖@�ʍH���̑傫�ȕӂ�̓y�t��E�݂��w���ƌ����B�s�����̑��݂������Ă����������B�p�����̖k���̎R�̐��Ζʂ̗ѓ������̎R�т̒J�Ԃɕs�������J���Ă����B�O�p�_�u�I�R�v�̐��������y�t��ɗ����鍑��9�����̖@�ʂ͌��݂͑傫���R���N���[�g�ŕ����Ă��邪�A�̂͊₪�I�o���Ă����Ǝv����B���̊R�̉��͂��̂܂ܐ�ɉ���A���J�ƂȂ��Ă��������a58�N�̐��Q�̌�A���H���J���ׂɍ��͏����d�@�ŕ���ɂ����Ƃ����B���ł����J�̍��Ղ͎c���Ă���B���������q�i��i�́j���j���˂ł͖������Ǝv�����B�����̈�p�̕s�����ł͍��ł��p�����̗�Ղ��s���Ă���ƌ����B�Â������ǂ�����̒J�Ԃɉ��{�������Ă���A���Ɋւ��̐[���s�������炵���B���̑q���u���ނ����v�̂悤�Ȃ̂ŁA�p������W���̌��i��ԓI�ɓ����j�̕��ƌ����Ӗ��ł́A�P�Ɂu�����i������j�v�ł͖������ƌ����l�����̂Ă���Ȃ��B�̂Ă���Ȃ��ƌ������u�����v�̕������肪�������R�őÓ��ȋC������B�������������q�ɂ���p������̗��R�̎R���ɏ��a58�i1983�j�N�ɐݒu���ꂽ�O�p�_�̓_�����u�I�R�i�����܁j�v�ł���̂͊����w���O���E�N���̌ꌹ�ł���ƌ����Ă���u����ʂ����v�Ȃǂƌ������̓����u���i����j�v��p�����u����R�v�ƌ������ƂŁA��͂荑��9�����e�̖@�ʍH���ӏ�������ꂽ�R�Ƃ������Ƃ��w���A���q�́u�����v�̂悤�ȋC������B�������ɋ�ʂ�������ޗ����Ȃ����T���Ă���B
�@���H�̃R���N���[�g�̖@�ʂƌ����A�p�������玭�q�R�Ɍ������r���A�J���g��t�߂ɂ��傫�ȃR���N���[�g�̖@�ʍH���������@��̗��݂ɂ���B�ׂ��̂т������@�쉈���̍k�n���A����R�n�Ɉ�U�r���ꏊ�ł���B�u���ރO���v�u���ރN���v�Ƃ��������̃V�J�́A�����u���ށv�̌ꊲ�Ȃ̂ŁA���{��Ƃ��Ắu�V�J���O���v�u�V�J���N���v�����́u�V�J�~�N���v�u�V�J�~�O���v�ƂȂ�B�n���p��ꌹ���T�ɂ������V�J���u���ށv�̈Ӗ��Ŗ������C������悤�Ɏg���ɂ́A���p������t���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B�V�J���O���͌����ɂ����̂ŃV�J���O���E�V�J�O���ƕω��������ƍl���Ă݂���A����������悤�Ɏv����B�V�J�O���E�V�J�N�����悩�A�V�J�������悩�A���q�Ə����ăV�J�����Ɣ������Ă����悤�Ȓ��������̂ŁA������ł̖��m�ȉ��Ƃ��Ắu���q�v�̕\�L����Ɏg���Ă������ŏ����ꂽ�u�l�_�y�v�̃V�J�O�������o�Ƃ������ƂɂȂ肻�������l�_�y�̗p���͂ǂ�����דI�Ȋ���������B�l�����̏ꍇ�Ɠ����ŁA�l�����ǂ݂Ȃ̂ɐ_�y���P�ǂ݂Ȃ͖̂�������ꂽ�����@���Ȃ��B�U�艼���̏��Ȃ��O�g�u�ŁA���Ղȁu���q�v�Ɂu�V�J�N���v�Ƃ���̂��l���Ă݂�Εs�R�ł����i�O�g�u�͌��{���`����Ă��炸�A�V�J�N���̐U�艼�������{�ɂ����������̂��ǂ����͕s���B�����͓p�������̏��́u���m�q�v�ɍ��킹�ĐU��ꂽ���̂��j�B���ƌ����ɂ̓J���g��ł����X�������C������B�����w���O���E�N���ł͂Ȃ��A�R�n�Ɉ͂܂ꂽ�p�����ŎR�n�̂��������ʂ���ׂɁA�R�n���w�����i��j��p�������̑q���l�́u�V�J�������v�u���ޕ��v�ł͂Ȃ��������Ǝv���Bsikamuwora �� uw ����܂��� u �ƂȂ������A�����@�����܂łɃ����I�ɓ������邱�Ƃ� uwo �� uo �ƂȂ�A���{��ɂ͕ꉹ�̘A���������X��������̂ŁA�X�ɖ�܂��ăV�J�����ƂȂ����̂ł͂Ȃ��������B�J���g����ӂ͛����@��̉͒J���A�J���g����͂��߂Ƃ���ᰂ����悤�ɋ��܂�ꏊ�ł���B�T�J�o���t�߂��㗬�ŒJ�͍Ăщ����قǂł͂Ȃ����L����B�܂��A��������̎O�p�_���ɂ���l���R�▯�Ԍꌹ�I�ɓ`���V�J�����ƌ������ɂ��Ή�����B���ꂪ���q�R�̖��̌��������̂ł͖����������B�n���Ɋg�[�������邱�Ƃ͖{���钷��g�c���ނ���c���j�̎w�E���鏊�ł���B�Ō�́u��v���u���v�Ɖ����Ȃ�u���i��j�v�͓����ɕt���Ȃ��̂ŁA�u�V�J���E���v�u���m�N�E���v�͓��{��Ƃ��ĕ��@�I�ɂ��肦�Ȃ��B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@���{��ł͓����J����/�J���O��A�����J����/�J�S���̂悤�� g �� m �̉��ɑ��ʂ�������B�V�J�O���i�l�_�y�j�̓V�J�������a�������̂ŁA�V�J�O���Ɂu���q�v�̎������Ă��āA�����Ɉ�����Đ����̃V�J�N���̓ǂݕ������ꂽ�ƌ��������ł͂Ȃ��������Bw ���̏����� m/g ���̑��ʂ��t�̏����ŋN�����Ă��������ƂɂȂ肻�������A�u�\�c�ꗍ���v�̗Ⴊ�����Ɏv�������ԃJ����/�J���O�̑��ʂɑ��āA���{�����Ƃ���҂Ƃ��ăV�J�����V�J�O�Ƃ͌����Ȃ��悤�ȋC�������i�u�d�|���v�Ƃ̍����������邩�炩�j�B�V�J���I���Ƃ��������傪�A�V�J�����Ƃ��������ɂȂ��Ă���łȂ��Ƒ��ʂ��N����Ȃ��C������B
�@�����́A�u�������v�����q�R�R���t�߂̘T������n�������A�G�X�q��E��V���Ȃǂ̊����w���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă������A�������J���g�⓯�l�A���Ƃ����ɂ͏������C������B�p�������牓�]���Ċ��Ǝw�Ăł��Ȃ��傫���ł���B�R�Ȃ���̒��x�̊��͍݂��ē�����O�ł���B
�@�O�g�u�ɂ͓y�t�쐅���̈�Ƃ��Ă̛����@��̗��H���p��������K���ւ̃��[�g��̒n���Ƃ��āu�����J�v���L����Ă���B���̒n���Ƃ̔z�猻�݂̒n�`�}�̎��q�R���痬��o��u�T�J�v�ɑ�������Ǝv����B�����J�́u���v�Ƃ͑������Ȃǂ̎��Ђł͂Ȃ��A�������ՂƓ`�������т̊ɌX�Βn���w���Ắu���i������j�v�̓]�a�Ƃ��l������B���̏ꍇ�͂��́u���v�Ɏ��ЂƂ��Ă������̂͌F�쌠�������ŁA���������_���חю����ו������u�����J�v�Ƃ����n���̉���\�L���`�����钆�Ő��܂ꂽ�ˋ�̂��̂ł������ƍl����B���̖���n�`����������o���鎛���J�ɉ����ĕs�m�����̂��鑾�����Ȃǂ̎��Г`�������A�����R�����Ƃ͂������̒r�̐ՂƓ`�����鎼�n������A���̉�����`�����ƌ�����퍑����̔N�L�̂���G�}��]�ˎ���̊G�����n���Ɏc����A�ϋɓI�Ɏ��̑��݂�ے肷�鍪���������̂ŁA�������玛�����������p�₵���Ƒ��ɁA���ɕ������ɓ]�a���đ������Ȃǂ̓`�������܂ꂽ�ƍl���Ă����B���̞����߂��Ɠ`�����邱�̒r�͎��q�R�חю��G�}�ł́u�V���E�u�r�v�Ƃ��������ƌ����B�P�ɐ���Ƃ��Ă̒n���ł������V���E�Y�i�����j�̓]�a���l������r�̖��ł������B
�@���X�ؒJ���L�̕���ƂȂ�퍑������́A�p�������ɊO����m�������B�R�Ԃ̏������V�J������/�V�J����/�V�J�O���������ɂ��ꂽ���Ƃ́A�܂�����������������Ȃ��B�m�͊����̓ǂݏ������o�����B�m�͑��l�ɋ�����ꂽ�n���u�V�J�����v���u�V�J�O���v�ƕ����A�R�E���R���ʂɔ�����ԓ��̂��鑺�͂���́u���ޕ��v�̉��̎��i�u�������v�Ȃǎ����͂����ł͖��Ȃ��j�ɁA�V�J�O���̉��ɍ��킹�ĎR���������\�L�Ŏ��q�R�ƌ��߂��B�����R�����O���炠�����̂��A�R���ƌ����������������̂��͍��ƂȂ��Ă͕�����Ȃ��B�܂��A���̎��q�R�̃s�[�N�ɂ�����O�ɕʂ̖��O���������̂��ǂ�����������Ȃ��B�m�ƌ𗬂̂������p�����̏Z�l�͂��̎��̎R�����V�J�����Ɉ��ނ��̂��ƒm���Ă����̂ŁA���q�R�Ə�����Ă��Ă��V�J�����T���E�V�J�������}�ƌĂ�ł����B���̌�A���́A���X�ؒJ���L���`���ʂ肩�ǂ����͂Ƃ������A�]�ˎ�����}����O�ɑޓ]�����B���̂������J�͎����J�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ă����B�]�ˎ���ɓ����Đ������������A���X�ؒJ���L�̍�҂������̕W���I�ȉ��ŌĂ��悤�Ƃ��Ď��q�R���l�_�y�R�Ə������B�����͊����ŏ����ꂽ�n���̉������{���̒n���ŁA���l���g���V�J�����T��/�V�J�������}���a�����������ׂ����̂��ƍl���Ă����̂�������Ȃ��B�������n���Ƃ͕�����m��Ȃ����O�̊Ԃł������Ő��藧���̂ł���A�a���Ă��邩�����Ă���Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A�����\�L�̕W���I�ȉ��ƈႤ�������Ă���Ƃ��������̂ł��Ȃ��A�a���Ă���悤�ɕ������Ă��Â����t��`���Ă��邱�Ƃ�����B�ォ�父�Ă�ꂽ�����̕����J�떳�������Ă���B�p�����̏Z�l�́A���ʂƗp���ŃV�J�O���Ƃ����l���������A��������܂őc�悩��`��鉹�A�V�J�����T���E�V�J�������}�Ǝ�ɌĂё������B�ʍ��Ȃǂ̂������ߗׂ̑��R���E�K�����ł������ĂԂ悤�ɂȂ��Ă����B�]�ˎ���̑�����300�N�ł��̎��̑ޓ]�̘b�����X�ؒJ���L��O�g�u�̂悤�ɕ����Ƃ��ē`��葱���A�V�J������艜�̍��������p�ɒ��̑q�܂œ�������A�����@�쉈���̃V�J������艜�ɂ��c������A�u���q�R�i�����ނ炳��j�v�̕����u���ޕ��i�V�J�����j�v���S�̒��̑��݂Ƃ��đ傫���Ȃ�u���ޕ��v�͖Y����A���q�R���Ȃ��V�J�����T���ƌĂԂ̂����Y����A�R�������ӎl�����Ɉ��ނƌ������Ԍꌹ�����܂ꂽ�B�����̎O�p�_���ʂł͒n���ɗ\�ߏ��������������Ɂu���q�R�v�Ƃ���̂ɏZ�l���u�V�J�����T���v�ƌĂԂ̂�s�R�Ɏv�����������痈���I�_�҂��R�����A����Ȃ�ƐV�����u�l���R�v�Ɠ_���Ɏ������Ă��B�������p�����ł͎��q�R�̕\�L������܂Ŏg��ꑱ�����B�ߑ�ȍ~�A���p�������P�Ȃǂ̋���ŁA�u�q�v�̎����P�ǂ݂ł̓N��/�O���Ƃ̂ݓǂވӎ������y���A�V�J�����͓p�����ł��V�J�O��/�V�J�N���ɒu��������Ă������B�p���������������O�a���A�X�ɂ͕��m�R�s�Ƃ��Ă��u���������܁v�ƌĂ�ł���B�����u���q�v���V�J�O���Ɠǂ܂������������X�ؒJ���L�̖ړI��300�N�̎����o�ĉʂ����ꂽ�B����œp�����قǂ͎��q�R�ƌ��ѕt���Ă��Ȃ��������I�����ł͓p��������`����Ă����u�V�J�������}�v�ƌ����Ăѕ��Ǝl�����̖��Ԍꌹ�`��������܂Ŏc����Ă����B���̂悤�ȗ���ł͂Ȃ��������Ǝv���B
�@�[�R�ѓ��̖��A�[�R�����q�R�̌Ăѕ��̈�炵���B
�@����R�̖��͐[�R�ѓ����ʏo���̓o�R�ē��̑��ɒn���̍]�ˎ���̊G�}�Ɍ�����B�ɔ\���}�ł͓p�����œy�t��ɍ��������̖��Ƃ��Ĕ��c��Ə�����Ă������A����ƊW������̂��낤���B�����������W�̓p�����̏������Ŕ���E���c��Ƃ����������͂Ȃ��悤�����A���c�ƌ����n���͒O�g�ł͂悭������B���y�[�W�ł͏��a58�N�̐��Q��Ǝv���鋴�̖��ł��炱�̐���u����v�Ƃ����B
�Q�l����
1�j�O�a���j�҂���ψ���C�O�a���j �㊪�i�ʎj�ҁj�C�O�a���C1995�D
2�j���c�����q��C���{�Җ��C���X�ؒJ���L�i�|�ѕ���2�j�C���{�Җ��C1972�D
3�j�V���C�V�c�S�i�O�a����v�쒬�j�̒n���i�����j�C�V���C1983�D
4�j�Ð�ΐ��E�i�˒咘�C�Ð쐳�H�C���c���C�O�g�u �V�c�S�C���m�R�j�k��C1973�D
5�j�i�˒咘�E�Ð�ΐ��C�Ð쐳�H�C�O�g�u�C�����o�ŁC1974�D
6�j�����H�G�}�T�v��ǐ}�C�O�a���j�҂���ψ���C�O�a���j �����ҁC�O�a���C1998�D
7�j�����W�C�V�c�S�C���s�{�̒n���i���{���j�n����n26�j�C�����M�F�C���}�ЁC1981�D
8�j���I���j�Ҏ[�ψ���C���I���j�C���Ɍ����I���C1987�D
9�j���c�ÍO�C���s�O�g�̎R�i��j �\�R�A���ɉ����ā\�C�i�J�j�V���o�ŁC1995�D
10�j���c�ÍO�C���q�R�C���s�{�̎R�i�V�E�����o�R�K�C�h25�j�C�R�ƌk�J�ЁC2004�D
11�j���c�m���C�䑽���a�c�L���Cpp38-44�C4�C�O�g�j�C�O�g�j���b��C1984�D
12�j���V�d�\�Y�C�ق��݂��ɁC���V�m�Y�C1977�D
13�j�����j�Ҏ[�ψ���C�����j�C�����j�Ҏ[�ψ���C1956�D
14�j�p�����j�Ҏ[�ψ���C�p�����j�C�O�a������p���x���C1957�D
15�j�V���C���n�����z�C�V���C1987�D
16�j�c��������C���ɒO�g�̎R�i���j�C�i�J�j�V���o�ŁC1992�D
17�j�p����{�n���厫�T�Ҏ[�ψ���C���s�{ �����i�p����{�n���厫�T26�j�C�p�쏑�X�C1982�D
18�j�팴�C��E�a�藝���Y�C�n���p��ꌹ���T�C�������o�ŁC1983�D
19�j���c�j�v�E�a�c�����E�k���ۗY�C�Ì�厫�T�C���w�فC1983�D
20�j���{�i�g�C���ꉹ�C�̕ϑJ�C�Ñ㍑��̉��C�ɂ��� ����сi��g���� ��151-1�j�C���{�i�g�C��g���X�C2007�D
21�j���c�ꋞ���C���� ���ꉹ�C�_�C���]���@�C1935�D
22�j�������v et al.�C�ɔ\�}�C���g���C2002�D
�g�b�v�y�[�W�� |
�@�������ց@ |