
富士見新道要部
黒点線は岩場と鎖場跡
赤点線は歩道と巻道
桃点線は新しい踏み跡

旧道萩原側から見上げる神部岩

 富士見新道要部 黒点線は岩場と鎖場跡 赤点線は歩道と巻道 桃点線は新しい踏み跡 |
 旧道萩原側から見上げる神部岩 |
 |
大菩薩峠萩原側旧道を登ると賽の河原に登りつく手前で笹原の奥の稜線にドーム状の大岩と大岩に向けて笹原と疎林の中を突き上げる岩場があるのが見える。この大岩は神部岩で、白ペンキで「神成岩 古」と文字が書かれている。姫の井沢から山腹を上がり、一列の岩場を登り「神成岩 古」を経て2000m標柱で稜線に出るルートである。以前は鎖場の連続するルート通称「クサリ場」で、鎖は腐食したので撤去されたというが、エスケープの緩い岩場の一ヶ所に鎖が残っているのを見た。
大菩薩峠萩原側旧道が姫の井沢を渡って少し上に富士見新道の入口がある。今の旧道が姫の井沢から逸れて右に曲がっていくのに対して富士見新道は姫の井沢の股の河原を直進する。富士見新道の今の旧道からの分岐の所が伏流気味で細くなっている右股が本流に見える左股に落ちる所である。左手の姫の井沢左股は富士見新道入口より上が湧水帯で導水管が散乱している。少し上がると左手の湧水帯が終わり左から沢音がしなくなるが今度は右股から沢音が大きくなり本流に見える流れがある。
道は左手の湧水帯の上の林の中を進み、神成岩西側下手辺りを起点とする、右股の水流に突き当たらんとするような長く太い蛇抜けの末端に出る。蛇抜けのゴロ石原にケルンが続いているが、左股の水のない河原をそのまま上がってくる細い踏み跡もある。
 入口 |
 右股湧水帯 |
 股の間 |
 蛇抜け末端に出る |
1820mで蛇抜けの右側の笹原の中に突然折れて入っていく。笹原から岩海斜面の林の中に入り薄い踏み跡を拾っていく。1870m辺りに碑伝のような形の標識が木に貼りつけてあり、三角形にルートが描かれており直進すると男道で右手に回り込んで勾配を緩めるのが女道ということのようである。一度目は踏み跡の濃い女道に進んだ。標識の字は擦れて読めないが男道が本来の富士見新道のようなことが書いてあるような気がしたのだが、帰宅後ネットの少し前の記録で直進の筋が男道で三角形の二辺に回り込む筋が女道で、その間の文字は男道も女道も「共に富士見新道」だったと知る。
女道をたどる人が多いようで踏み跡は女道の方が濃い。二度目に通った直登の男道は一直線の浅い谷地形を登っていくが再び女道と合流するまでの半分くらいで踏み跡はほぼなくなる。引き返して女道を登り直す人が多いのかもしれない。女道は少しトラバースしてから男道よりは傾斜の緩い斜面を登る。1930mの岩尾根の末端付近で男道と女道が合流する。合流する緩くなった所は男道の踏み跡もはっきりしている。
 蛇抜けから笹原へ |
 碑伝型道標 |
 男道 |
 女道 |
岩尾根の末端の下の笹原に塩山市の注意看板がある。ここから核心部だが登りつくのは標高2000mの標柱の所なので高さにして100mほど残すだけであり短い。正面に見える第一の鎖場跡の岩尾根には鎖が張ってあった頃の鉄杭が残っているのが見えるが岩尾根の右手の谷地形の草付きの中を登る踏み跡があり、急傾斜だが草を掴むこともなく登れる。
第一の鎖場跡は三段になっていて段の合間から右手の谷地形と出入りできる。一番上の段が少し長く、下と中の段は短い。中の段の上から左に犬走りがあり、その奥の傾斜の緩い低い岩場に岩に打ち込まれたアンカーに繋がったままの鎖が残っているが、鎖に頼らなくても上り下りできる。上の段の上部は細いがボコボコの岩でホールドは多い。第一の鎖場跡のホールドの少ない所は足場が切られているような気がする。
第一の鎖場跡の岩尾根の上はまだ林の中だが、すぐ上がガレ場で明るくなる。ガレ場の上に第二の鎖場跡の岩尾根が見えている。第二の鎖場跡の岩尾根の中段のテラスに踏み跡に従ってガレ場から上ると、テラスの向こうの谷間に鎖が見える。テラスの床の岩に白ペンキで直線の矢印と折れ線の矢印が二つ消えかかって示してあって、テラスから下りるのに左のガレ場へ直に下りても一旦右に下りて左に回り込んでも下の第一の鎖場は左下方であると示しているようである。ガレ場からテラスへ岩登りで直に上がるのも鎖場だったようである。左寄りが簡単だが鎖のアンカーはホールドの少ない右寄りの上にある。
第二の鎖場跡のテラスより上は壁が立って高さがあって登るのは大変そうである。向かって右寄りに足場が多いが鎖のアンカーは壁のような左寄りの上にある。テラスから垂壁の下の左奥の落ちている鎖の付け根と思しき辺りの上に洞窟があり、洞窟の額に「フジミ穴観音 古」と白ペンキで書かれているのが見える。テラスから短いへつりで穴観音の下に行く。落ちている鎖の付け根は抜いたアンカーごと立ち木の根元に巻いて結んであって、撤去された鎖が回収されずに地面に残っていたのを誰かが転用のつもりで結んだようである。或いは谷間を登る為の転用ではなく、へつりの為の転用のつもりであったのがテラス側の固定が悪くて谷間に落ちているのか。穴観音の洞窟は這えば何とか中に入れそうな低い天井で、中に観音像などは見当たらない。何となく毛色の違う自然石の平石が一枚あった。
 第一の鎖場跡末端 岩登りせずば右の谷間へ |
 第一の鎖場跡の 頭から振り返る |
 第一の鎖場跡の 上のガレ場 |
 右からテラスへ |
 テラスの上 ペンキで矢印が 二つ書かれている |
 テラスから 親不知方面を 見る |
 テラス下から 直登 左寄り |
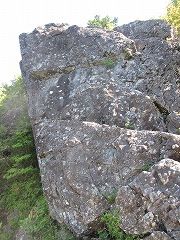 テラス上の壁 左寄り |
 テラスの下を 回り込んで左へも |
 左の巨岩の間を 抜けて |
 左から テラスへ上がる |
 テラス上の壁 右寄り |
 テラス上の壁の上 |
 テラスから穴観音へ |
 穴観音 |
 穴観音から振り返る |
穴観音の向かって右の岩に取り付いて登る。後半は傾斜が緩んで第三の鎖場跡の下の向かいのガレ場に出る。向かって左の岩は低く傾斜が緩く上に踏み跡があってやはりガレ場に上がるが新しくこなれていない。下るならこちらだと思う。
穴観音の向かって右上の岩場の傾斜が緩む辺りから右手の樹林に戻るように入る踏み跡があり、第二の鎖場跡の頭に出る。第二の鎖場跡の頭から笹茂る樹林の中の尾根線上となる踏み跡を登ると上のガレ場の第三の鎖場跡の取り付きの向かいに出る。ガレ場を渡らずガレ場に沿って低木林の中の踏み跡を登り続けると上の方は草付きとなって第三の鎖場跡の岩場無しで神部岩の右下に上がる。穴観音の右上の岩場をそのまま登っても第三の鎖場跡取り付き向かいのガレ場に出る。ガレ場の中で第二の鎖場の頭から上がってくる樹林の踏み跡と合流する。ガレ場を渡って第三の鎖場跡の岩尾根末端の傾いたテラスから岩壁に取り付く。正面は手掛かり少なく難しそうだが左端はボコボコしており鎖が無くても登れるが突き出した岩尾根なので高度感がある。傾いたテラスの向こうの藪に第三の鎖場跡の岩尾根を巻く踏み跡があって神部岩の左下に出るが、新しくこなれていない。ボコボコの岩壁の上も岩尾根が続くが傾斜は緩い。すぐに大きな卵のような神部岩の真ん前に出る。神部岩にも白ペンキで「神成岩 古」と書かれている。
 穴観音 右の岩を登る |
 上の方は傾斜が緩む |
 ガレ場に出る |
 第三の鎖場跡 正面 |
 左端はホールド多い 上から |
 神部岩下に着く |
 神部岩 額の白ペンキの文字 |
 ガレ場からの巻道は右の 樹林沿い 上から見る |
 ガレ場から神部岩直下に 上がる巻道の踏み跡 |
神部岩の左手の下には岩屋状の庇があり数人なら雨宿りできそうである。左から神部岩を巻いて上がって振り返って神部岩を見ると尖っており、旧道から見るドーム状や直下から見る卵状とは印象が違う。「神成岩 古」と白ペンキであったが、介山荘近くの案内図では「神部岩」となっている。
岩科小一郎(1959)の「大菩薩連嶺」に上萩原の「神部神社の山宮、すなわち、観音の像を置いた所を大菩薩峠の神成岩だといい、その説を信ずる人が神成岩の上に観音の木造を建立したことがあった」とあるが、岩科小一郎自身は神部神社の山宮が大菩薩峠辺りにあったとは考えていなかったようである。また、「カミナリ岩」を「唐松尾根を登り切って右へ行った地点にある平岩」としており岩科小一郎のいう神成岩/カミナリ岩は今の雷岩のことである。神部社の社掌が「山宮は妙見岩なりといわれた」ともあり、後の神部神社に関わりのある人が、岩科小一郎が先客妙見尊があるから神部社の山宮が妙見岩とは賛成できぬとする妙見ノ頭と、神仏混淆にしても観音という仏を祀って神成はおかしいとする雷岩を外して、残簡風土記(近世初頭の成立とされる日本惣国風土記で偽書とされる)に山梨郡の東限とされる神部山の神部神社山宮の故地として神部岩或いは「神成岩 古」を修行場を兼ねた富士見新道としたのか。
 神部岩下庇状 |
 神部岩 回り込んで振り返る |
 2000m標柱 |
参考文献
チンボー,大菩薩 富士見新道,わんだらおやじの山登り(2024年11月3日閲覧)
ひらさん,大菩薩嶺(富士見新道)〜小金沢山〜牛奥ノ雁ヶ腹摺山縦走 (山梨県・甲州市)ひらさんのHighトレッキング,ひらさんのHighトレッキング(2024年11月3日閲覧)
岩科小一郎,大菩薩連嶺,朋文堂,1959.
甲斐志料刊行会,甲斐風土記 残簡,甲斐志料集成3 地理部2,甲斐志料刊行会・大和屋書店,1933.
トップページへ |
資料室へ |
大菩薩嶺メインへ |